
枝師藤原玉夫には、最晩年にまとめた、「りんごと共に40年」という回想録があることからもわかるように、浅岡一が信州の教育界に強烈な刺激を与え、山路愛山が新聞界に大きな活力を吹き込んで、それぞれ7年なり4年なりの歳月をもって去っていったのとは異なり、その生涯を信州りんごを育てるために捧げ尽くしたのである。
-- 私は大正10年4月20日に本県農事試験場に赴任し、昭和17年8月に退職したのであるから、その間21年、そして更北村丹波島に果樹園を経営すること19年であって昭和36年4月20日をもって満40年間りんご栽培と取り組んだわけである。勿論この40年間は私の一生であり、また実に変転極りない期間であったとも云える。--
と藤原は「りんごと共に40年」の冒頭に記しているのだが、大正10年4月、広島からこの山国にやってきた農業技師にとって、りんごを見るのは初めてといってよい素人園芸家だった。彼が最初に手がけた仕事といえば、われひと共にりんご栽培の科学的基本を学ぶべく、農事講習会に講師として、のちに北大学長となりりんご博士の異名をもった青森県主任技師島善隣を招いたことにあった。
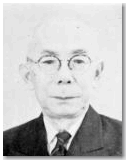 |
| 島 善隣* |
県会議事堂に集まった県下各郡農会の技術者たちを前にして、島善隣は3日間、明治以来青森県が蓄積してきたりんご栽培のノウハウを何ら隠すところなく披歴したあと、往生地、長沼、湯田中の各地でりんご園を視察した。信州のりんご栽培の幼稚さをあますところないまでに浮き彫りにしたといってよいだろう。
島善隣の紹介で、青森のりんごの神様ともいうべき外崎嘉七がりんご剪定講習会にやってきたのは大正12年の秋のことだ。実地指導に選ばれたのは、模範的と見られていた往生地の丸々一ニのりんご園だったのだが、外崎嘉七は丸々農園に一瞥をくれると、ききとりにくい津軽弁で「こんなに密植しあっては剪定してもなにもならん。隣の樹を切ればよし、さもなければ剪定はせぬ。」という意味のことを言って、数百人の参会者たちの驚きの中で、丸々農園のりんごの太枝をかまわずバッサバッサと伐っておとしていった。
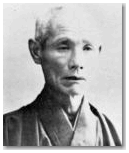 |
| 外崎嘉七 |
-- 私は島先生の講習会と外崎翁の剪定実地指導を併せ、正に信州りんごの黎明を告げるを心に深く刻みつけられた。--
と藤原玉夫は書いている。この若い技師は島善隣と外崎嘉七の触発によって、生涯を信州の地に埋めることを決意したかのように、大正から昭和にむけて、りんご栽培の指導に精魂を傾けることになったおもむきがある。
昭和3年、長野県のりんごの主産地は
長野市・・・往生地、上松 更科郡・・・共和、篠ノ井、塩崎
上水内郡・・長沼、浅川、神郷、中郷、芋井
上高井郡・・小布施、川田 下高井郡・・・中野周辺
埴科郡・・・坂城周辺 北安曇野郡・・大町周辺
諏訪郡・・・中洲、下諏訪
と定着し、りんご園は五百五十町歩ともなったが、昭和恐慌のもと繭価の暴落に比して信州りんごが安泰だったのは、県下のどのりんご園にも足跡を踏み入れぬところのなかったほどの藤原技師の活躍に負うところが多かったことを忘れるわけにはいかない。害虫駆除、整枝剪定、品種の改良はいずれも、県農事試験場で藤原玉夫が解決したといってよい。もっとも、藤原の活躍には、打てば響くような反応がりんご栽培者にもあったことにもささえられたことはまちがいない。
戻る つづく
*隣は俗字で本来は「おおざとへん」 善隣と書いて「ヨシチカ」 。
生まれた時が日清戦争の5年前の明治22年で両国間の雲行きが怪しくなっていた為
日清の親善を祈願して神官だった父親が命名したと思われる。(澤田英吉)
|