|

島崎藤村が、「若菜集」を世に問うたのは、たしか明治三十年のことだ。 そこに盛られた有名な「初恋」という四連の詩が生まれたのは、明治二十九年、藤村が東北学院の英語教師として仙台にいたころのことだ。
まだあげ初めし前髪の
林檎のもとに見えしとき
前にさしたる花櫛の
花ある君と思ひけり
やさしく白き手をのべて
林檎をわれにあたへしは
薄紅の秋の実に
人こひ初めしはじめなり
わがこころなきためいきの
その髪の毛にかかるとき
たのしき恋の杯を
君が情に酌みしかな
林檎畠の樹の下に
おのづからなる細道は
誰が踏みそめしかたみぞと
問ひたまふこそこひしけれ
この詩を素直に読めば、木曽の馬籠に生まれ育った藤村の少年の日の追憶が、原風景としてその奥底に流れている。ここにうたわれている前髪の少女は、隣の大脇家のお文さんだというのも定説になっている。
藤村の年譜をみれば、急速に衰亡していく木曽馬籠宿の運命を象徴するかのように、小学四年の藤村は長兄秀雄に伴われて上京し、姉の嫁ぎ先の高瀬家に預けられているから、この詩に歌いこまれた原風景は、少なくとも明治十四年までのものでなければならないのだが、そのとき、木曽の馬籠に「林檎畠」があったのか。
明治十二年、上水内郡三輪村の原善之助が、アメリカから帰朝した津田仙から苗木を譲りうけて植栽したのが信州リンゴの嚆矢(こうし)だという説をとるならば、木曽の馬籠に当時すでに「林檎畠」があって、薄紅の実がなっていたということはありえない光景だということになる。
後年、藤村は「微風」という作品の中でこんなふうに回想している。
−その辺は旧本陣時代の屋敷跡ということでしたが、私が覚えたころはすでに桑畑で、林檎や桐などが畠の間に植えてありました。隣の石垣の上には高い壁が日に映って見えました。それがお文さんの家でした。−
小学四年のときに郷里を出なければならなかった藤村が、上京以来ふたたびその地を踏んだのは、継祖母あたる大脇桂子の葬儀に長兄秀雄に代わって出席した明治二十四年十一月の末のことだ。 その時、かつて本陣の屋敷跡であったところが桑畑になっており、その間に桐やりんごの樹が植えてあったというのは考えられぬことはない。
しかし、木曽地方に林檎園が今も無いことを考えれば,桑畑の間にリンゴの樹が植わっていたというのは、詩人の脳裡にきざまれた幻影だったかもしれないが、明治二十四年の十一月といえば、すでに信州りんごは東京から遠路やってきた元本陣の坊ちゃんの餐応のために食卓に並べられるまでになっていたであろうことは想像がつく。 まだ中央線は通っていなかったから、横川までの鉄道のほかは、碓氷峠も和田峠も歩いて登らねばならず、中山道の沿道に、薄紅に実った珍しい舶来の果物が詩人の目を強くひいたということも考えられる.
「若菜集」はそれまでの新体詩のスタイルでうたわれているけれども、そこに盛り込まれた生命はそれまでとは全く異なる新しいものであったことを考えれば、「林檎畠」ということばもまた欠くことのできぬ素材であったことだけはまちがいない。
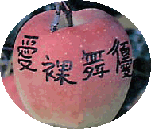
戻る つづく
|