
60年の来し方を振り返って、私が最も親しんできた果物といえば、もちろん、りんごだ。 葡萄や梨も好きだけれども、多くの果物には旬があって、短い時期がすぎれば、またたくまに他の果物にとって変わられてしまうのだが、 果物としてのりんごの生命は永く、夏の早出しの青りんごにはじまって、春先もみがらの底から取り出して食べる最後のりんごまで数えれば、ゆうに八ヶ月近く私はりんごに親しんでいることになる。
わたしが食べてきたのは、もっぱら”信州りんご”だ。 ”青森りんご”とか”津軽りんご”とはいわないのに、”信州りんご”という言葉があるのはなぜだろう。 津軽の人たちは口数が少ないばかりか、あえて、”津軽りんご”と名乗らなくても、りんごをみれば人はたいていそれが青森産と受け止めてくれるだろうという王者の自信があるからなのかもしれない。
それにひきかえ、青森産を追いかけて、常にぴったりと二番手について走っていくためには、品種や味の改良はむろんのこと、出荷の時期などについても、たえず工夫をこらしてこなければならなかったのが信州のりんごではなかったろうか。”信州りんご”のネーミングには、そんな工夫や苦心のひびきがこめられているのであろう。
 |
| 倭錦(やまとにしき) |
わたしの子供のころには、倭錦というお相撲さんのしこ名のようなりんごや、祝というむやみに酸っぱいりんごが主流をしめていたが、戦争が始まると、国光と紅玉の時代となり、それが長いことつづいた。わたしが東京に出てきてからも、ありがたいことに、秋になると、ふるさとの匂いとともに”信州りんご”だけは欠かさず送られてきた。
インドやデリシャスといった片仮名のりんごは平和の到来を意味したが、スターキングによって「蜜の味」を知ってしまった者にとっては、倭錦や祝はなんだか弥生時代の果物のような気がしてくることがある。
とはいえ、王鈴とか世界一などという信州りんごにまじって、むつや津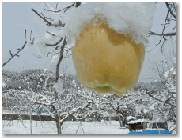 軽といった”信州りんご”とめまぐるしくめぐりあった末に、限りなく美味になったふじを毎日食べていると、あの素朴な倭錦をもう一度皮もむかずに噛みしめてみたいというようなぜいたくな欲求がめばえてきたりするこのごろだ。 軽といった”信州りんご”とめまぐるしくめぐりあった末に、限りなく美味になったふじを毎日食べていると、あの素朴な倭錦をもう一度皮もむかずに噛みしめてみたいというようなぜいたくな欲求がめばえてきたりするこのごろだ。
わたしがこれまでに口にした”信州りんご”はおそらく指折り数えてみれば、読んだ書物の数に匹敵するかもしれないのだが、ふと思えば、信州りんごに関する書物を一冊も読んでおらず、信州りんごがへてきた苦闘の歴史について何の知識も持ち合わせていないのは、いかにも不謹慎というものではないか。 そんな反省の上に立って、「林檎園の風景」に目をやってみよう。
つづく
sound
by nocturne
|